
お知らせ
【こども誰でも通園制度】に関する記事の監修を行いました
保育と療育のこれからを考えるきっかけに
このたび、合同会社テラセルが運営するWebメディアにて公開された記事
『こども誰でも通園制度 どう変わる?保育と療育の関係性について』の監修を、
当法人理事長・小田知宏が担当いたしました。
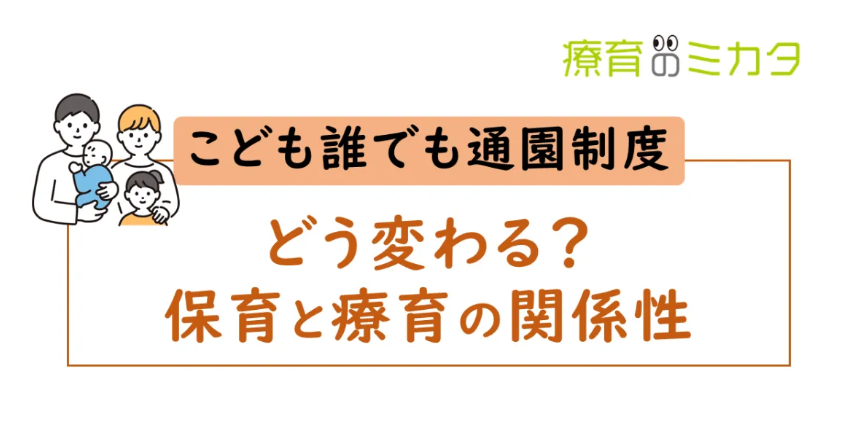
本記事では、2026年4月より本格実施予定の「乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)」について、
制度の背景・目的・課題から、保育・療育現場への影響までを、わかりやすく解説しています。
「すべてのこどもの育ちを支える」新制度の意義
この制度は、保護者の就労状況を問わず、すべての未就園児が保育施設に通える機会を保障することを目的に設計されています。
背景には、少子化・産後うつ・児童虐待など、近年深刻化する子育て家庭の孤立や不安があります。
制度を通じて以下のような前向きな変化の可能性が描かれています。
-
「預け先がない」という不安からの解放
-
保護者が地域や専門職とつながれる機会の増加
-
こどもが社会との接点を早期に持てる環境の提供
-
支援の“網”の外にいた家庭へのアプローチ
こうした変化は、保育と療育の現場にも大きな影響をもたらします。
保育と療育、連携の必要性が高まる時代へ
制度の施行により、保育所ではより多様なこどもを短時間・不定期に受け入れる必要が出てきます。
その中には、発達に特性をもつこどもや、支援が必要な家庭も含まれる可能性があります。
そのため、記事では次のような変化が予測されています。
-
保育士が特性に応じた対応力を求められる
-
保育現場が“療育的な視点”を持つことが重要になる
-
地域の療育機関(児童発達支援事業所など)との連携が不可欠に
こうした連携は、療育側にも新しい動きを生み出します。
例えば、保育園から特性が気になるこどもが紹介されるケースの増加や、保育者への情報提供・研修のニーズなどです。
監修にあたり込めた思い
今回の監修にあたっては、当法人が大切にしてきた「ちがいをまるごと受けとめる」という視点を軸に、
制度の意義が単なる“預かりの拡大”ではなく、こどもと保護者が安心して地域につながれる仕組みとして伝わるよう心がけました。
記事の中では、以下のようなポイントが描かれています
- 「発達に『困りごと』がある」とはどういうことか
- 周囲が“ちょっと気になる”と感じたときの具体的なサイン
- 特性を否定せず、その子らしさを大切にする接し方
- 相談機関や療育支援へのつながり
特に、「気づきの早さが支援の質を左右する」というメッセージは、制度設計を超えた本質的なテーマです。
保護者・保育者・支援者が孤立せず、互いにつながりながらこどもを支えていく仕組みが、いま求められています。
制度の本格実施に向けて、いま私たちにできること
こども誰でも通園制度の本格実施まで、残された時間はわずかです。
制度を持続可能で意義あるものにするためには、地域の現場が声をあげ、準備し、学び合う必要があります。
記事は、そうした対話のきっかけとして、また保育・療育の未来を共に考えるためのツールとして、多くの方に読んでいただきたい内容となっています。
ぜひご一読ください。



